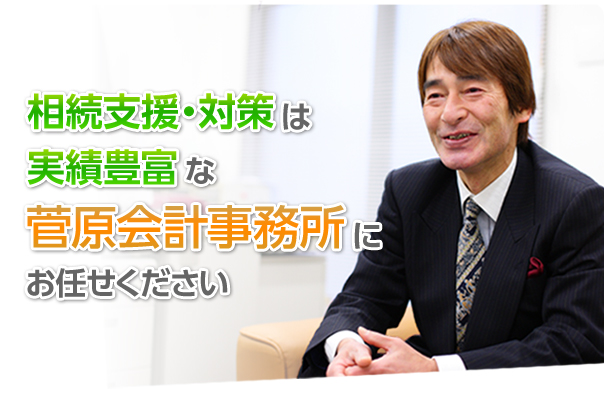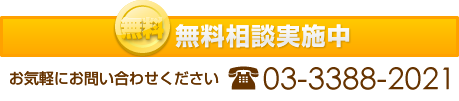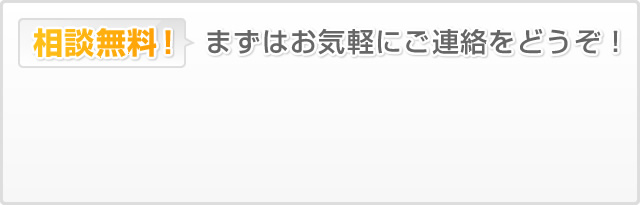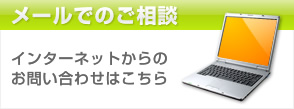ブログ
2015年7月17日 金曜日
民法相続編 その22・・・遺言⑤
民法相続編その22は、遺言の効力を取り上げます。
1、 遺言の効力
遺言は遺言書の作成が適法であれば、作成時に成立したことになります。ただし、効力が発生するのは、遺言者が死亡したときにとなります。
また、遺言に停止条件が付けてあるときは、条件が成就して初めて効力が生じます。同じように遺言の記載内容を実現するために特別な手続きが必要な場合も、手続き完了までは確定的な効力は生じません。
たとえば、遺言に推定相続人の廃除が記載されていたとします。この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をし、裁判所の審判で廃除が確定して初めて、遺言は遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じることになります。
2、 無効になる場合
遺言も法律行為である以上、民法総則に定める意思表示の規定の適用が問題となります。これらの規定は、遺言の性質に適合する限り適用されます。
遺言に関しては、作成の方式が定められておりこれに違反した遺言は無効となります。15歳未満の遺言、意思無能力者の遺言も無効です。また、犯罪行為を唆すなどのような公序良俗に反する遺言も無効になります。
同じく、錯誤により作られた遺言も無効ですし、詐欺や強迫による遺言や取り消すことができます。
3、 遺言の撤回
有効に作成された遺言を効力が発生する前に阻止することを、遺言の撤回といいます。遺言の効力が生じる前ならば、撤回は自由にできます。
普通の人は、遺言をいったん作成しても気が変わることがあります。撤回を認めないとすると「遺言は遺言者の最後の意思表示」という遺言本来の意味が崩れてしまいます。遺言は遺言者の最終的な意思を尊重するための制度なのですから、撤回できるのは当然のことです。
投稿者 | 記事URL
2015年7月10日 金曜日
民法相続編その21・・・遺言④
民法相続編その21は、遺言の④で公正証書・秘密証書を取り上げます。
3、 公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書によって遺言を作成する方法です。証人2人以上の立ち合いをつけ、遺言者は遺言の内容を公証人に口述します。公証人はこれを筆記し、のちに遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。ついで、遺言者と証人、公証人が署名押印して完成します。
なお、言語機能に障害がある人は手話通訳や筆談による方法が認められます。また、病床にある場合、公証人に出張を依頼することができます。ただし、認知症等で意思能力に問題がある場合には、医師の診断書等が必要です。
この方式の特徴は、遺言の原本が公証人役場に保管され、偽造、破棄、隠匿の恐れがないことです。また、遺言者の意思に基づき向こうの主張の恐れが少ないこともあります。家庭裁判所の検認手続きが不要で、遺言検索システムによる検索が容易であるというメリットもあります。
しかし遺言内容を他人に知られるという欠点があり、公証人への手数料も発生します。
4、 秘密証書遺言
秘密証書遺言の作成方法は、まず遺言者は遺言内容を記載した証書に署名・押印します。次いで、証書を封じ証書に押印した印鑑でこれを封印します。そして公証人1人と証人2人以上の前にこの封書を提出し、自分の遺言書である旨と遺言書が他人によって書かれているときは筆記者の氏名、住所を申述します。公証人は、証書が提出された日付および遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名押印し成立となります。
ここでの申述も、手話通訳でできます。遺言内容を記した証書は、他人の筆記でもワープロで作成してもかまいません。
この方式のメリットは、遺言書の内容を秘密にすることができることと公証人の手数料が節約できます。一方で、公証人が遺言の内容を確認することができないため、内容に不備があったり紛争の種になったりする可能性があります。また、家庭裁判所の検認が必要です。
投稿者 | 記事URL
2015年7月3日 金曜日
民法相続編その20・・・遺言③
民法相続編その20は、遺言の③で遺言の方式について取り上げます。
1、 遺言の方式
遺言の方式には、普通方式と特別方式の2種類があります。
特別方式の遺言とは、臨終、船舶の遭難、伝染隔離など危急の状況時に作成されるものです。つまり、普通方式の遺言が不可能なときのものですから普通方式によって遺言することができるようになった時から6か月生存するときは特別方式によった遺言は効力を失
います。
普通方式の遺言の場合も、民法の定める方式に従って作成しなければ無効となります。たとえば、「夫婦だから1通の遺言書で」などは共同遺言となり無効となります。この普通方式の遺言には、次の三つの作成方法があります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
2、 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその全文を自筆し、日付、氏名も自筆であることが要求されます。そしてこれに印鑑を押さなければなりません。したがって、遺言者の口述した内容を他人が筆記したり、ワープロや録音テープで作成したりした場合は自筆証書遺言とは認められません。
また日付は暦日を記載するのが通常ですが、「第何回目の誕生日」のように作成日が特定できるのであれば有効となります。印鑑は認印で構いませんし母音でも認められます。
公正証書以外の遺言は、相続の開始後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言は、費用も手間もかからず簡単にできます。しかし紛失や隠匿の恐れがあり、方式を間違えたりして無効になる恐れがあります。したがって自筆証書遺言は、争いが起きない場合に限ります。そうでなければ、あくまで公正証書遺言を作るまでの暫定的なものと考えるべきです。
投稿者 | 記事URL
2015年6月26日 金曜日
民法相続編その19・・・遺言②
民法相続編その19は、遺言の②で死因贈与他を取り上げます。
(4) 共同遺言は禁止されている
遺言には、単独での意思表示の確保が絶対に必要になります。そのため2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。共同遺言は、個人が単独で意思表示をするという点で、また各人が遺言を自由に撤回できないという点で問題になるからです。
しかし、禁止されている共同遺言とは、共同で一つの意思表示をした場合をいいます。ですから、同じ用紙に各人が独立した遺言を書いた場合は、別個の独立した意思表示であり共同遺言の禁止に抵触することはありません。
(5) 遺言は撤回できる
遺言はいつでも撤回することができます。遺言は遺言者の死亡によって効力を発する制度ですから、遺言者の存命中には効力がなく撤回されても不利益を被る者は存在しないからです。また複数の矛盾する内容の遺言がある場合には、新しい遺言が優先します。
(6)死因贈与
死亡後に財産を譲与する方法には遺言によらないで、贈与契約によって贈与者の死亡を条件に贈与を行う死因贈与という方法もあります。死因贈与は、通常の贈与と同じく贈与者が贈与の意思表示をし、相手方が受諾することによって効力を生じます。口頭でも贈与契約は成立しますが、死因贈与の場合当事者の一方である被相続人が既に死亡していることになり受贈者のみの挙証では問題がありましょう。贈与契約書の作成が必須と言えます。
遺言は、一定の様式によることが必要ですが、遺言書に瑕疵がある場合、たとえば自筆証書遺言が法定の要式行為を書いており家庭裁判所の検認で却下されたときは、遺言の執行(土地建物の登記など)ができないこととなります。このような場合でも、その遺言書が実質的に生前における当事者間の死因贈与契約であるとして、死因贈与により財産を取得することが認められる可能性があります。
死因贈与の対象が不動産の場合には、契約の締結により仮登記ができます。相続人がいない借地権者について地主との間に生前に死因贈与契約を締結し、仮登記をすることにより相続対策となります。
投稿者 | 記事URL
2015年6月19日 金曜日
民法相続編その18・・・遺言①
民法相続編その18は、遺言の①です。
「遺言」
(1) 遺言とは何か
遺言は、被相続人の自由な意思の表明であり、その人が死亡したときに法的効力を発生します。遺言は本人の真意による最終的意思であるかどうかを確認するため、及び遺言を慎重にさせるために、そして偽造や変造を防止するために一定の様式が要求されています。この方式に違反する遺言は無効となります。
(2) 遺言できる内容
遺言の内容は法に定められた事項に限られます。その事項とは、
① 認知
② 後見人や後見監督人の指定
③ 遺贈、遺贈減殺方法の指定
④ 寄付行為
⑤ 相続人の廃除および廃除の取消
⑥ 相続分の指定および指定の委託
⑦ 特別受益者の持ち戻し免除
⑧ 遺産分割方法の指定および指定の委託
⑨ 遺産分割の禁止
⑩ 共同相続人間の担保責任の指定
⑪ 遺言執行者の指定および指定の委託
⑫ 信託の設定
です。これ以外の事項について遺言がなされても無効となります。
(3) 遺言作成には意思能力が必要
遺言は誰にでもでき、行為能力は必要ありません。ただし、物事に対する一応の判断能力(意思能力)は必要とされています。ですから、成年被後見人であっても判断能力を一時回復していれば、2人以上の医師の立ち合いを得て単独で有効な遺言をすることができます。被保佐人・被補助人の場合には、保佐人・補助人の同意なしに有効な遺言が作れます。
未成年者の場合は、満15歳に達していれば単独での遺言が可能です。なお、遺言は意思表示の一種ですから意思能力のない時の遺言は無効になります。また、詐欺や強迫による遺言は取り消すことができます。
投稿者 | 記事URL
カテゴリ一覧
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (4)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (5)
- 2018年8月 (7)
- 2018年7月 (8)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (5)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (7)
- 2017年11月 (7)
- 2017年10月 (8)
- 2017年9月 (8)
- 2017年8月 (6)
- 2017年7月 (8)
- 2017年6月 (9)
- 2017年5月 (8)
- 2017年4月 (8)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (8)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (9)
- 2016年10月 (8)
- 2016年9月 (8)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (9)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (4)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (3)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (6)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (6)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (6)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (3)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (6)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (7)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (7)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (7)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (7)
- 2012年1月 (7)
- 2011年12月 (11)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (8)