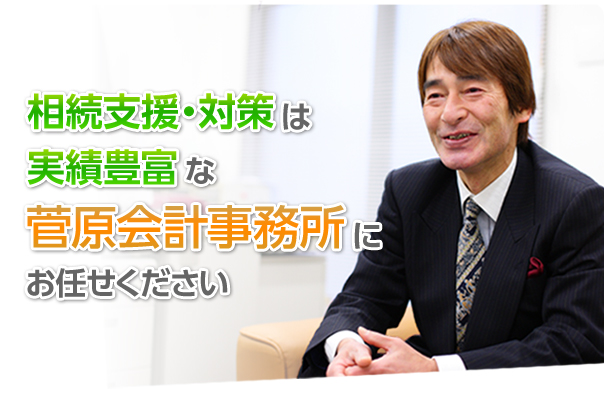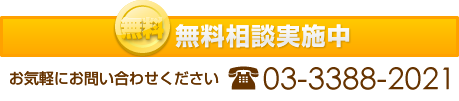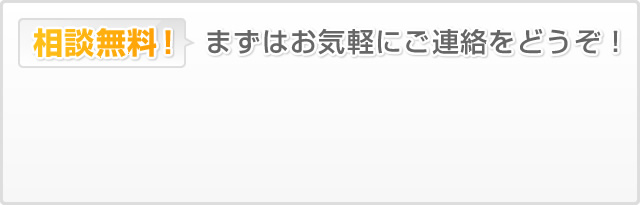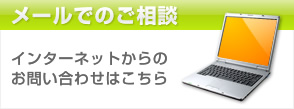民法相続編
2015年6月26日 金曜日
民法相続編その19・・・遺言②
民法相続編その19は、遺言の②で死因贈与他を取り上げます。
(4) 共同遺言は禁止されている
遺言には、単独での意思表示の確保が絶対に必要になります。そのため2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。共同遺言は、個人が単独で意思表示をするという点で、また各人が遺言を自由に撤回できないという点で問題になるからです。
しかし、禁止されている共同遺言とは、共同で一つの意思表示をした場合をいいます。ですから、同じ用紙に各人が独立した遺言を書いた場合は、別個の独立した意思表示であり共同遺言の禁止に抵触することはありません。
(5) 遺言は撤回できる
遺言はいつでも撤回することができます。遺言は遺言者の死亡によって効力を発する制度ですから、遺言者の存命中には効力がなく撤回されても不利益を被る者は存在しないからです。また複数の矛盾する内容の遺言がある場合には、新しい遺言が優先します。
(6)死因贈与
死亡後に財産を譲与する方法には遺言によらないで、贈与契約によって贈与者の死亡を条件に贈与を行う死因贈与という方法もあります。死因贈与は、通常の贈与と同じく贈与者が贈与の意思表示をし、相手方が受諾することによって効力を生じます。口頭でも贈与契約は成立しますが、死因贈与の場合当事者の一方である被相続人が既に死亡していることになり受贈者のみの挙証では問題がありましょう。贈与契約書の作成が必須と言えます。
遺言は、一定の様式によることが必要ですが、遺言書に瑕疵がある場合、たとえば自筆証書遺言が法定の要式行為を書いており家庭裁判所の検認で却下されたときは、遺言の執行(土地建物の登記など)ができないこととなります。このような場合でも、その遺言書が実質的に生前における当事者間の死因贈与契約であるとして、死因贈与により財産を取得することが認められる可能性があります。
死因贈与の対象が不動産の場合には、契約の締結により仮登記ができます。相続人がいない借地権者について地主との間に生前に死因贈与契約を締結し、仮登記をすることにより相続対策となります。
投稿者