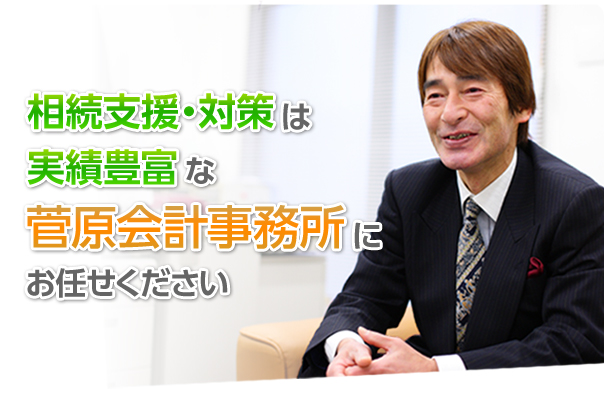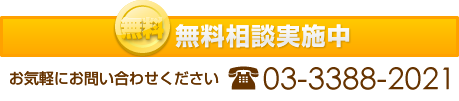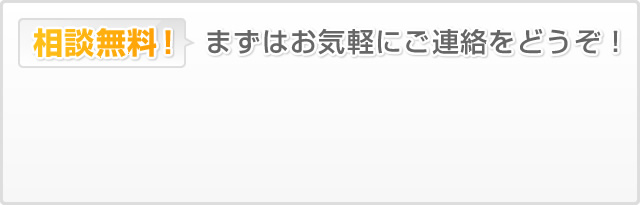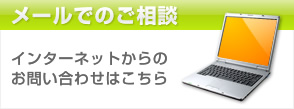ブログ
2014年10月3日 金曜日
平成27年度税制改正の行方
平成27年度税制改正の要望が、各府省庁から出そろいました。その中で相続・贈与税・譲渡所得(資産税)に関連する項目をピックアップしてみます。
「内閣府から」少子化対策・子育て支援の税制改正の要望
内閣府からは少子化対策として、「結婚・出産・育児資金の一括贈与制度の創設」、「三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置の創設」が、子育て支援として「子育て支援に係る税制上の措置の検討」、「くるみん税制の延長・拡充」が要望事項に掲げられています。
このうち子育て支援に係る項目は所得税・法人税関係なので今回は少子化対策の二つを取り上げてみます。
1、子・孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置の創設(内閣府・金融庁)
(1)目的
この制度は、少子化の背景の一つにある結婚・妊娠・出産・育児に係る経済的負担を緩和し、あわせて高齢者の資産の世代間移転による経済活性化を目的とするものです。昨年創設された「教育資金一括贈与制度」の結婚・出産費用版といったところで、これらの費用ももともと贈与税は非課税(その都度の贈与に限る)とされていましたが、一括贈与制度の創設を要望したものです。
(2)内容
・信託の機能を活用し、結婚、妊娠、出産、育児に係る払出しを行う信託スキームを使って、子・孫へ贈与を行った場合について、贈与税の課税対象としないこととする。
・少子化対策に資する事業を行う公益法人等へ信託財産の一部を寄附する制度とする場合には、当該寄附相当額につき、贈与税非課税での払出しを可能とする。
・子育てに要する支出を所得税制上の控除の対象にする
(3)注目点
少子化対策としての効果は限られていると思いますが、創設されればインパクトはありそうです。制度設計では非課税金額と信託期間をどうするのか、育児費用の範囲をどう定めるか注目してみていきたいと思います。
投稿者 | 記事URL
2014年9月26日 金曜日
生前贈与の落とし穴
「生前贈与の落とし穴」
生前贈与をするうえでうっかりしそうな落とし穴を上げてみました。
・贈与したつもりが、税務署からは単に名義を変えただけで相続財産とされる場合がある。
・贈与税の方が相続税よりも税率が高い。
・不動産を生前贈与する場合には、「不動産取得税」や「登録免許税」が課税されるが、これらの税金は、相続時に比べると高い税率が設定されており、その分費用がかかってしまう。
・相続人等に対する相続開始前3年内の生前贈与は、相続財産とみなされる。
・相続開始年分の贈与はなかったものとみなされる。
相続時精算課税の落とし穴
・相続税の基礎控除引き下げにより、相続時精算課税の選択が不利になってしまう。
・相続時精算課税で生前贈与をしてしまうと、小規模宅地の特例が適用できない。
・上記と同様に物納も適用できない。また、延納選択時の不動産等から除かれる。
・相続時精算課税を選択した年以後の少額の贈与についても贈与税の申告が必要である。
・受贈者が先に死亡し、結果的に二重課税となる場合がある。
相続時精算課税制度は、一度選択すると取り消しができません。メリットも大きいですが、デメリットも多くリスクを十分把握したうえで活用したいものです。
投稿者 | 記事URL
2014年9月19日 金曜日
相続税の節税対策・・・生前贈与の活用
来年からの相続税の増税を控え、節税に関する相談が増えています。相続税を節税するには、多くの方法がありますが、生前贈与を行い、相続税のかかる財産を減らすのがいちばん確実でかつ効果的な相続税対策です。
ただし、生前贈与と言っても多くの制度を理解しその活用方法を検討する必要があります。また、うっかりしやすい落とし穴にも注意が必要です。
「生前贈与による節税チェックリスト」
1 暦年贈与を活用する・・・□
2 相続時精算課税を活用できないか?・・・□
3 扶養義務者(孫等)への生活費・教育費等の贈与は可能か?・・・□
4 贈与税の配偶者控除の活用についてはどうか?・・・□
5 住宅取得資金の贈与の活用についてはどうか?・・・□
6 世代飛び越しの贈与の活用はどうか?・・・□
7 教育資金の一括贈与の活用についてはどうか・・・□
8 相続人以外の者への贈与は可能か?・・・□
9 贈与物件は値上がりの可能性の高いものを設定しているか?・・・□
10 生命保険料の贈与はどうか?・・・□
11 収益物件の生前贈与はできないか?・・・□
12 法人成りによる相続対策は検討したか?・・・□
13 事業承継税制の適用はできないか?・・・□
14 農地の納税猶予は適用できないか?・・・□
15 特別障害者信託財産の活用は・・・□
16 非居住者間の国外財産の贈与は活用できないか?□
投稿者 | 記事URL
2014年8月15日 金曜日
相続税・贈与税で平成26年より適用される事項 その2
2、 医業継続に係る相続税または贈与税の納税猶予等の新設
(1)概要
持分の定めのある医療法人については、その持分に相続税が課されたり持分の払い戻し請求を受ける可能性があったりすることなどから医業の承継に問題を生じる恐れが指摘されていました。そこで平成19年医療法人法改正により、医業継続の観点から持分のある医療法人は設立できないこととなりました。また経過措置により継続している医療法人については、持分のない医療法人へ円滑に移行を進める観点から、相続税または贈与税の納税猶予等の制度が創設されました。
(2)相続税の納税猶予
相続または遺贈により相続人が持分のある医療法人の持分を取得した場合において、その医療法人が申告期限において認定医療法人*である時は、担保の提供を条件としてその持分に係る相続税について認定移行期間の終了時まで納税が猶予されます。
*認定医療法人とは、平成26年改正医療法の施行日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいいます。
(3)猶予税額・利子税の納付
移行期間内に持分のない医療法人に移行しなかった場合または認定の取り消し、持分の払戻し等の事由が生じた場合には、猶予税額を納付します。
この場合相続税の申告期限から機関に係る利子税を合わせて納付しなければなりません。
(4)猶予税額の免除
納税が猶予された相続人が、認定移行期間の終了時までに持分のすべてを放棄した場合には、その猶予税額は免除されます。
(5)税額の控除
相続人が、相続または遺贈により認定医療法人の持ち分を取得した場合において、その相続人が相続開始の日から申告期限までにその持分の全部または一部を放棄した時は、前記(2)納税猶予の規定の適用ではなく、その放棄された部分に相当する相続税額を税額から控除します。
投稿者 | 記事URL
カテゴリ一覧
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (4)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (5)
- 2018年8月 (7)
- 2018年7月 (8)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (5)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (7)
- 2017年11月 (7)
- 2017年10月 (8)
- 2017年9月 (8)
- 2017年8月 (6)
- 2017年7月 (8)
- 2017年6月 (9)
- 2017年5月 (8)
- 2017年4月 (8)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (8)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (9)
- 2016年10月 (8)
- 2016年9月 (8)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (9)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (4)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (3)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (6)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (6)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (6)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (3)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (6)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (7)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (7)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (7)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (7)
- 2012年1月 (7)
- 2011年12月 (11)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (8)