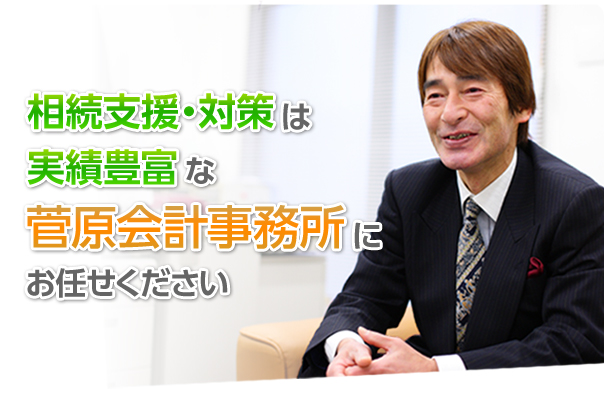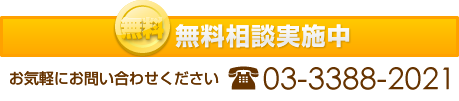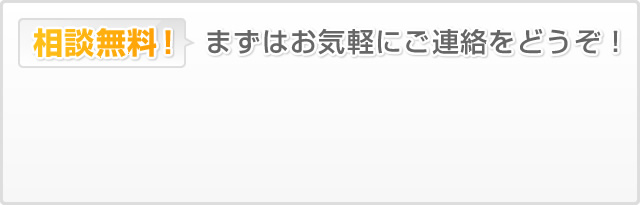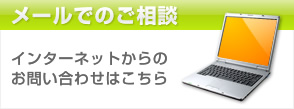ブログ
2015年4月3日 金曜日
「民法 相続編」その3・・・相続人②
民法相続編その3は、相続人の2回目です。
「相続人②」
*胎児(民886条)
胎児は、相続については既に生まれたものとみなします。法律上は、胎児がお爺ちゃんの財産を代襲相続することもあり得ます。
*相続欠格者(民891条)
相続欠格者とは、
①故意に被相続人や先順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者、
②詐欺または脅迫によって被相続人の遺言に影響を与えた者、
③被相続人に遺言書を偽造、変造、隠匿等した者、
④被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴や告発をしなかった者を言います。
遺言書を隠すと相続権を失います。遺言執行を妨げるため自筆証書遺言を保管者から交付を受け返還も検認手続きの申し立てもしなかった場合に、遺言書の隠匿に当たるとされた事例があります。
*廃除者(民892条)
廃除者とは、以下の理由で被相続人が家庭裁判所に廃除請求をして相続権を失った者を言います。
①被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を与えた者
②その他著しい非行があった者です。
いわゆる放蕩息子を相続人から廃除することができますが、実務的には余程の非行が行われた場合でないと難しいようです。
投稿者 | 記事URL
2015年3月31日 火曜日
民法 相続編 その2 「相続人①」
民法 相続編 その2 は 「相続人」について説明します。
「相続人」
相続人には配偶者たる相続人と血族相続人がいます。血族相続人は、先順位の者だけが相続人となります。
1、 子及びその代襲者の相続権・・・第1順位(民887条)
(1)子の相続権
被相続人の子は相続人となります。子供が数人いる場合には、同順位で相続します。実子、養子、嫡出、非嫡出子を問わず同順位で相続人になります。
*嫡出子とは法律上の婚姻関係にある夫婦の子供を言い、非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の子供を言います。また認知されていない子は相続人になれません。
(2)代襲相続
相続人である子が、①相続開始以前に死亡、②相続人の欠格事由に該当、③廃除によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
(3)再代襲
(2)の規定は、代襲者が①相続開始以前に死亡、②欠格事由に該当、廃除によって相続権を失った場合について準用します。子の代襲者である孫が相続開始以前に死亡していた場合には、ひ孫が相続人となります。
投稿者 | 記事URL
2015年3月27日 金曜日
「民法 相続編」 その1・・・相続とは?
今回から民法の相続編を取り上げていきたいと思います。
相続の実務を行っていると相続人の方にとって大変なのは、1,相続の手続きの煩雑さ 2,遺産分割で揉める場合がある 3,相続税等の申告・納税が複雑であることの三つです。特に遺産分割で揉めた場合には、相続手続きは滞り、相続税の取り扱いでは不利な取り扱いがあり、基本的に遺産で納税できないため納税も困難です。調停に至るケースはめったにありませんが、弁護士に代理を依頼することになり調停も民法上の相続分にしたがって和解を進めるケースがほとんどです。相続争いをしても家族全体でみれば何もいいことはないのです。
遺産分割の際に少しでも役立つよう、民法における相続の基本について簡潔に説明していきたいと思います。
1、相続とは何か?
(1)相続の開始(民882条)
相続は、人の死亡により開始します。亡くなった人を被相続人と呼び、財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。
(2)相続が開始する場所(民883条)
相続は、被相続人の住所において開始する。したがって、相続に関する争いの裁判の管轄は被相続人の死亡時の住所を管轄する裁判所にあります。また、相続税の申告も被相続人の住所地の所轄税務署に申告しなければなりません(相法27条)。
(3)相続の効力(民896条)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産上の一切の権利義務を承継します。ただし、一身専属のものについては承継しません。
投稿者 | 記事URL
2015年3月24日 火曜日
消費税の確定申告
所得税・贈与税の確定申告は平成26年分については、3月16日(月)が期限で当事務所は無事終了いたしました。一息ついたもののつかの間だけで、今度は個人事業者の消費税の確定申告期限が3月31日に迫っています。
個人事業者の消費税については、前年と比較して特に変わった点はないのですが、消費税そのものが平成26年4月1日から8%に増税されています。したがってその計算に当たっては、原則3月までの5%の税率の取引と4月以降の8%の税率の取引と区分して計算する必要があります。さらに、経過措置で4月以降の取引であっても例外的に5%で課税されるものがありこれも区分しなければなりません。経過措置の適用があるものは、水道光熱費・通信費・リース料など多岐にわたります。
経過措置については、オフィシャルサイトの2014年6月24日「消費税率引き上げ時の税務上の取扱い その2」をご参照ください。
http://www.sugawarakaikei.jp/blog/2014/06/post-201-917372.html
当事務所では、顧客様の消費税の確定申告は所得税の確定申告と同時に終了しています。残っているのは、例によって自分の消費税の確定申告だけです(笑)。今頃になって、3月末支払の4月分の家賃は8%で、5月支払の水道代は5%などと処理していると嫌になってきます・・・(泣)。
投稿者 | 記事URL
2015年3月20日 金曜日
上場株式の譲渡損失の繰越
2014年3月13日のブログ「上場株の確定申告・・・プロの選択」
http://www.sugawara-kaikei.com/blog/2014/03/post-319-787449.html
で 上場株式の譲渡損失は平成25年分の株式等の譲渡所得等と通算すると10%しか税の還付の対象とならないので、平成26年まで繰り越して20%の税率で通算するほうが有利だと説明しました。
また、その際の注意点として株価は上下するものなので、繰り越したはいいが譲渡利益が出ないと何もならないので予想配当と確定譲渡利益の範囲で繰り越すようお勧めしていることも書きました。
さて、今年の確定申告でその通算しなかった繰越損失がどうなったか?結果を明かしましょう。
最も損失が大きかったAさんの場合は、予想される配当等の金額の範囲で繰越しました。配当といっても証券投資信託が主で確実とは言えないのですが、もともとの金額が大きいので結構リスクもありました。結果は、26年分も所有株式の含み損は消えないまま売却はできず、配当のみで前年より2%ほど多く収入がありました。したがって、無事繰越控除することができました。
他の方は、予想配当の金額が少なかったので繰越額が小さくあまり効果はありませんでした。株の値動きから比べたら微々たる金額ですが、一応節税にはなりました。
プロの選択は正しかったということにしておきましょう(笑)。
投稿者 | 記事URL
カテゴリ一覧
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (4)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (5)
- 2018年8月 (7)
- 2018年7月 (8)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (5)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (7)
- 2017年11月 (7)
- 2017年10月 (8)
- 2017年9月 (8)
- 2017年8月 (6)
- 2017年7月 (8)
- 2017年6月 (9)
- 2017年5月 (8)
- 2017年4月 (8)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (8)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (9)
- 2016年10月 (8)
- 2016年9月 (8)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (9)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (4)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (3)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (6)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (6)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (6)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (3)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (6)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (7)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (7)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (7)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (7)
- 2012年1月 (7)
- 2011年12月 (11)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (8)