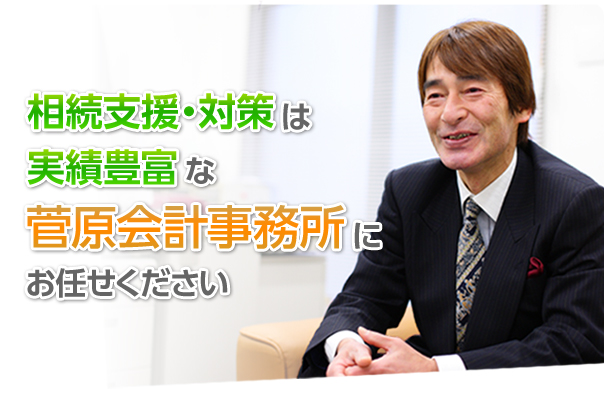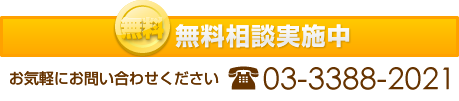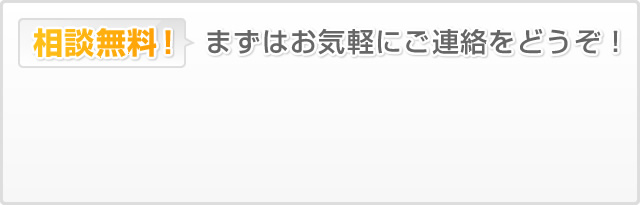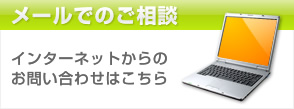ブログ
2015年8月18日 火曜日
(前編)相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合には
相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。しかし、相続税の申告期限までに遺産の全部または一部が共同相続人等によって分割されていない場合には、相続税の特例が受けられません。以下の記事をご覧ください。
/blog/images_mt/%E6%9C%AA%E5%88%86%E5%89%B21.pdf
投稿者 | 記事URL
2015年8月7日 金曜日
民法相続編その25・・・遺言⑧
民法相続編はいよいよ最終回、遺言の⑧で引き続き遺留分を取り上げます。
5、 遺留分減殺の方法
遺留分権者の遺留分を確保する範囲内で、減殺請求ができます。
減殺の対象となる遺贈や贈与が多く存する場合は、まず、遺贈から減殺されます。遺贈が複数ある時は遺贈の額に応じて比例配分します。そして減殺される贈与が複数ある時は、時間的に後の贈与から減殺され、順次前の贈与に及びます。
6、 遺留分減殺請求権の時効
遺留分の減殺請求権は、遺留分権者が相続の開始および贈与や遺贈を知った時から1年、相続開始の時から10年で時効によって消滅します。なお、相続の開始後は自由に遺留分を放棄することができますが、相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
7、遺留分でもめないために
遺留分に抵触しない内容の遺言を作成するのが望ましいのですが、自宅しか財産がない、会社の株は後継者に渡したい、事業用の土地を後継者に渡したい等やむにやまれぬ状況も考えられます。
あらかじめ財産を相続税財産評価通達により評価して、遺留分相当の代償金を支払わせるよう遺言するのは効果のある方法です。
遺留分の減殺方法を指定することも考慮に値します。遺留分の減殺請求があった場合「特定の財産についてだけ減殺するものとする」旨の遺言は有効です。
また、法的に効力はなくとも、自身の意図を組んで遺言に従ってほしい旨の付言はつけるのが望ましいと思います
投稿者 | 記事URL
2015年8月4日 火曜日
都市部の路線価は上昇傾向
111国税庁が7月1日に公表した平成27年分の路線価では、全国平均は前年分を0.4%下回って7年連続の下落となりました。以下は、エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。
/blog/images_mt/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%B7%AF%E7%
B7%9A%E4%BE%A1%E4%B8%8A%E6%98%87.pdf
投稿者 | 記事URL
2015年7月31日 金曜日
民法相続編その24・・・遺言⑦
民法相続編その24は、遺言の⑦で遺留分について取り上げます。
1、 法律により保障される遺留分
遺留分とは、一定の相続人に最低限確保されている相続分のことを言います。被相続人が相続人以外の者に対して贈与や遺贈をした場合でも、侵すことができないものです。
人は自分の財産を自由に処分することができます。これは生前に限らず遺言すれば死後の処分にも及びます。しかし遺言者の意思であっても、遺言者の死後に残された近親者の生活のことも考慮する必要があります。そこで遺留分の制度が認められるようになったのです。
2、 遺留分の権利者
遺留分の権利を持つ者は、相続人のうちでも、配偶者、直系卑属、直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
また、相続廃除や相続欠格、相続放棄によって相続権を失った者には遺留分はありません。
3、 遺留分の割合
遺留分の割合は、権利者の組み合わせによって次のように変わってきます。
① 直系尊属のみが相続人のときは、相続財産の3分の1
② その他のときは、相続財産の2分の1
遺留分を算定する際の基礎となる相続財産とは、被相続人が死亡した際に持っていた財産の価額に、相続開始前の1年以内に行った贈与などの財産の額を加算して、その額から債務の額を控除して決定します。したがって、相続分を算定する際の相続財産とは異なります。
4、 遺留分減殺請求
遺留分の権利者は、被相続人から得た相続財産の額が遺留分に達しない場合には、遺留分が侵害されたとして、多く相続した者や遺贈・贈与を受けた者に対し減殺請求ができます。
しかし、遺留分を侵害する贈与や遺贈があった場合でも、その贈与や遺贈が無効になるわけではありません。また、遺言により遺贈の減殺の順序や減殺の割合を変えることができます。
投稿者 | 記事URL
2015年7月24日 金曜日
民法相続編 その23・・・遺言⑥
民法相続編その23は、遺言の⑥で遺言の撤回方法と遺言執行者について取り上げます。
4、遺言の撤回の方法
遺言撤回の方法とは、前の遺言と矛盾する内容のものを新たに作成すればよいのです。この場合撤回という文言を使用する必要はありません。何らかの形で前の遺言の効力を否定する表現をするだけで十分でしょう。
同じく遺言者が前に記した遺言とは矛盾するような行為をした場合も、遺言の矛盾する部分については撤回されたものとみなされます。たとえば、「ある建物をAに残すという遺言をしておきながら、遺言者が生前にその建物を売却した」などはこれに当たります。
遺言者が遺言をいったん撤回した後、次の遺言でこの撤回を再度撤回した場合遺言者の真意が明らかでないので、最初の遺言は復活しないこととされています。
5、遺言執行者と遺言執行
遺言を作成しても、相続が発生した後にその遺言の内容を実現させなければなりません。不動産の相続登記や預貯金の名義書換といった遺言の内容を実行する実務を行う権限を持つ者を遺言執行者といい、遺言で指定することができます。公正証書遺言の場合は、公証人が介在するため遺言執行者を定めないケースはほとんどないと思われますが、自筆証書遺言の場合は、記載がないことがよくあるので注意が必要です。
遺言執行者の指定がなされてなかったり、指定者が遺言執行者への就任を拒絶した場合等は、相続人・受遺者等の請求することにより家庭裁判所が選任します。
遺言執行者には、相続人や受遺者がなることも可能ですが未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。また、遺言をめぐって争いが生じた場合、遺言執行者が相続人の間に入る事態も考えられます。相続争いが想定されるような場合には、報酬の問題がありますが専門家を遺言執行者として指定するほうがよいでしょう。遺言執行報酬は、相続財産の中から支払われるので、遺言で定めておくのが望ましいでしょう。
投稿者 | 記事URL
カテゴリ一覧
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (4)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (5)
- 2018年8月 (7)
- 2018年7月 (8)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (5)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (7)
- 2017年11月 (7)
- 2017年10月 (8)
- 2017年9月 (8)
- 2017年8月 (6)
- 2017年7月 (8)
- 2017年6月 (9)
- 2017年5月 (8)
- 2017年4月 (8)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (8)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (9)
- 2016年10月 (8)
- 2016年9月 (8)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (9)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (4)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (3)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (6)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (6)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (6)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (3)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (6)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (7)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (7)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (7)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (7)
- 2012年1月 (7)
- 2011年12月 (11)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (8)