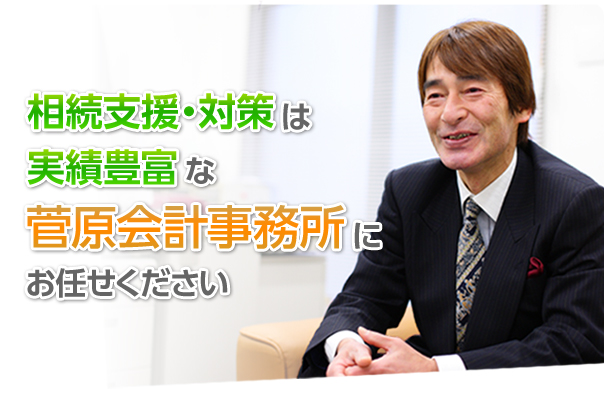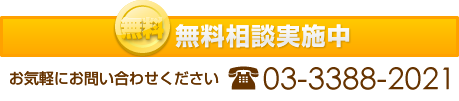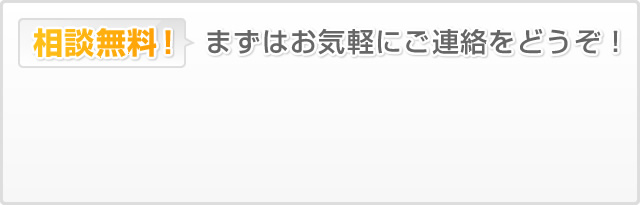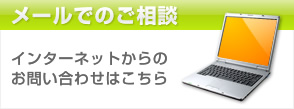ブログ
2014年2月5日 水曜日
平成25年分確定申告の準備は整いましたか!
平成25年分所得税の確定申告書の提出及び納付期限は、平成26年2月17日から3月17日までです。
◆確定申告が必要な主な人
①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入がある人
②給与しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与や退職所得以外の所得金額が20万円超える人
③土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金を譲渡した人
④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃貸収入を得ている人
⑤公的年金等の収入金額が400万円を超える人、などです。
また、
⑥平成25年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人
⑦医療費や寄附金控除の適用を受ける人、災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。
◆昨年と比べて変わった主な点
①復興特別所得税の創設
東日本大震災からの復興財源確保のため復興特別所得税が創設されました。平成49年までの25年間に亘ります。復興特別所得税の額は、基準所得税の額の2.1%相当額です。
②給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
③特定支出控除の見直し
税理士、公認会計士、弁護士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)が追加されました。また、適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1に縮減されました。
④特定役員の退職所得課税の改正
勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税が廃止されました。
⑤国外財産調書制度の創設
12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産調書を提出しなければならなくなりました。
◆準備すべき主な必要書類
1、所得控除他一般的なもの
①生命保険料控除証明書
②国民年金・年金基金の支払証明書
③地震保険料控除証明書
④医療費の領収書(平成25年中に支払ったものに限る)、
⑤寄附金の領収書及び証明書等
⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの
⑦住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約書、住民票、登記簿謄本など、です。
また、
⑧給与所得者は源泉徴収票
⑨年金所得者は年金等の源泉徴収票
2、不動産所得のある方
① 家賃の収入明細・通帳の写し
② 固定資産税の領収書
③ 火災保険料の領収書
④ 修繕その他諸費用の領収書
⑤ 地代家賃の支払明細
⑥ 借入金返済表
3、譲渡所得のある方
① 売却・購入時の契約書
② 売却・購入時の登記費用領収書
③ 仲介手数料・印紙代等領収書
④ 登記事項証明書
⑤ 自宅の場合住民票(除表)
4、事業所得のある方
① 各種帳簿
② 収入金額の明細
③ 必要経費の明細・領収書
④ 事業用預金通帳の写し
⑤ 売掛・買掛・未払費用明細
⑥ 固定資産台帳
投稿者 | 記事URL
2013年12月26日 木曜日
平成26年度税制改正大綱より・・・資産税関係の改正点
平成26年度の税制改正で資産家の方に影響があると思われる改正点をピックアップしてみました。
1、相続税の取得費加算については、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とされます。平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の譲渡から適用。
2、ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止されます。平成26年4月1日以後の譲渡から適用。
3、少人数私募債利子は、発行時期に関係なく平成28年1月1日以後に支払を受けるものから総合課税となります。
4、消費税の簡易課税のみなし仕入れ率が見直され、不動産業は第6業種となり仕入率40%に引き下げられます。平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用。
この中で最も影響の大きな改正は、1の相続税の取得費加算の改正です。相続税を納付するために土地を売却する際の所得税等が大きく変わります。相続税の大増税に加えダブルパンチと言えるでしょう。
会計検査院の指摘を受けての改正ですが、相続税を取得のためのコストと考えるのであれば適用される期間の制限(相続税申告期限から3年)を撤廃すべきだと思います。
投稿者 | 記事URL
2013年12月12日 木曜日
与党平成26年度税制改正大綱発表
与党は、12月12日に平成26年度税制改正大綱を発表しました。下記リンクをご参照ください。
https://d8dc8da5651c9cc8a1b4-03f6d6805dfc858e9204edf35efce76b.ssl.cf1.rackcdn.com/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf
投稿者 | 記事URL
2013年12月6日 金曜日
年内にできる個人の節税対策・・・所得税対策(不動産・事業所得者の場合)
年内に駆け込みでできる節税対策をご紹介します。
①消耗品等の購入
1個当たり10万円未満の少額減価償却資産を購入します。また、青色申告の場合30万円未満でも申告書に記載することを要件に必要経費算入が認められています。太陽光発電設備など即時償却が認められるので検討してみてはいかがでしょうか?
②固定資産の修繕
店舗や賃貸用建物、車両その他の事業用固定資産の修繕も年内に済ませるよう検討しましょう。
③短期前払費用の活用
1年以内に役務提供を受ける短期の前払費用を支払った場合、支払った年度の必要経費に算入できます。家賃・地代・利息・保険料(事業用の火災保険や従業員対象の生命保険など)等があります。
④不良資産の廃棄・除却
棚卸資産や固定資産に不良在庫があれば処分・除却を検討しましょう。また不良債権があれば必要経費に算入できないか検討しましょう。
⑤小規模共済の活用(年払制度あり)
小規模企業共済は、個人事業主向け(小規模な法人の役員も可)に国が用意している退職金共済です。年末までに新規加入または増額すれば所得控除の対象になります。月払いの人は年払いにすれば控除が増えます。また、年末までに1年分を前納すれば支払った年の所得控除の対象となります。
⑥簡易課税の選択の可否(来年が課税事業者の場合)
個人事業主は、消費税についても検討しなければなりません。平成26年が課税事業者となる場合には、この12月末までに原則課税と簡易課税のどちらか有利な方を選択することができます。簡易課税を選択する場合には、12月末までに簡易課税選択届出書の提出が必要になります。
投稿者 | 記事URL
カテゴリ一覧
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (4)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (5)
- 2018年8月 (7)
- 2018年7月 (8)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (5)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (7)
- 2017年11月 (7)
- 2017年10月 (8)
- 2017年9月 (8)
- 2017年8月 (6)
- 2017年7月 (8)
- 2017年6月 (9)
- 2017年5月 (8)
- 2017年4月 (8)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (8)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (9)
- 2016年10月 (8)
- 2016年9月 (8)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (9)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (4)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (3)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (6)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (6)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (6)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (3)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (6)
- 2013年2月 (9)
- 2013年1月 (3)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (7)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (7)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (7)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (7)
- 2012年1月 (7)
- 2011年12月 (11)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (8)